日本製三浦春馬
山形県
取材日:2018年3月頃?
●米沢牛の畜産農家 遠藤さん
〒991-1356
山形県西置賜郡小国町
訪問先・関連のURL

米沢牛銘柄推進協議会
会長・米沢市長 中川 勝氏おすすめの
最高の米沢牛ステーキ肉
肉の断面に見える細やかな、脂の霜降りが美味しさの秘密
【対談・考察】

LIVE JAPAN
山形の絶品ブランド牛「米沢牛」
🍎林檎
+act 2018年6月号掲載 【米沢牛の畜産農家を訪ねて】
~品質・味・生命・すべて愛情だと感じさせられた。~
書き出しの文、「この時期にこんなに降るのは珍しい」と。
今回の話しぶりから、「2018年の3月頃では?」と思いました。
また、この時の春馬さんの装いは、4月号の秋田県と8月号の青森県の取材時と同じ。
恐らく、2017年暮れから2018年の春先にかけての取材・撮影と推察しました。
この度の取材地は、山形県西置賜郡小松町。
四大和牛のひとつ、米沢牛の畜産農家の遠藤さん。
因みに、四大和牛とは(神戸牛・松坂牛・近江牛・米沢牛)。
畜産農家には、肥育農家・繁殖農家があり、遠藤さんは、両方手掛けているそう。
「肥育農家」とは、仔牛を購入して、飼育し主に食肉として出荷する。
「繁殖農家」とは、母牛を肥育し、交配させて産ませた仔牛を販売する。
さて、米沢牛のブランドとしての条件とは?
①置賜地方に居住。
②「米沢牛銘柄推進協議会」認定生産者であること。
③登録された牛舎で18か月以上継続して飼育されていること。
④生後32か月以上であること。
と、厳しい条件があります。
遠藤さんは、畜産専業は三代目、兼業は十代以上前からという歴史ある農家さんですね。
独自の飼料を作っていて、それを食べさせることで、牛の良し悪しが決まるというほど、食に拘りをもっていますね。
人間もそうですが、やはり生き物にとって、食べ物の良し悪しは軽視できない部分ということが分かりますね。
体温で溶けるような融点の低い脂で、口飽きせずいくらでも食べられる肉を目指しているというだけあり、召し上がった春馬さんも、絶賛のお味に、「どんどん食べられる」と感想を述べていますね。
-column-には、春馬さんのいつも通りの、思慮深さを感じる言葉が残っていますね。
東日本大震災で被害にあったのは、人間だけではなかったということ。
また、遠藤さんのお父様が、働く本人が好きでやらなくてはとの言葉に、本人にストレスがあったら、牛達に伝わるという意味があったのでは?と、生き物を扱う仕事の厳しさと愛情が感じられる話をしています。
遠藤さん一家は、後継者がちゃんと育っています。お父様の、無理に継がそうとは思っていなかったのだけれどという言葉の中には、物事の本質をしっかりと考えていらっしゃる姿勢(牛の事を大切に思っているということ)が、受け取れて感心しました。
こちらも、他で見聞きしてきた職人さんたちと同様、親の背中を直接見ることが出来る環境というのが、後継者を育てるのには大変重要であり、自然なことなのだと思いました。

チャールス・ヘンリー・ダラス氏
米沢牛銘柄推進協議会/米沢牛の高い品質と美味しさを全国へより
チャールス・ヘンリー・ダラス氏
*****************
上杉鷹山は藩校を開校し、その名を「興譲館」とした。
その興譲館で、明治四年から八年までの間教鞭を執ったチャールス・ヘンリー・ダラス氏が、故郷を懐かしんで四つ足の動物は食べないとされた米沢の地で、牛肉を食べたのが食用としての米沢牛のはじまりである。
その味わいに、いたく感動したダラス氏は、任期を終え、米沢を離れる際に一頭の牛を横浜へ連れていった。
彼の友人たちは、その牛肉の旨さを口々にほめそやし、それがいつからか「米沢牛」が全国に広がるきっかけとなった。
上杉鷹山公が生涯を学問とし、十七歳で米澤藩主となってから、藩の繁栄と民のために尽力した上杉鷹山の残した精神は、百余年たった今でもはっきりと、息づいている。
以上、関連URL内の、米沢牛の歴史の中に書かれています。
有名な故事ことわざが出てきますし、米沢牛の恩人として、チャールス・ヘンリー・ダラスという英国人が生きた時代が、やはり五代友厚氏の時代と被り、興味深かったです。
書いているうちに、美味しい牛肉が食べたくなりました。
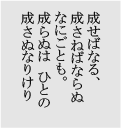
上杉鷹山公の言葉
🕊💖希望
林檎様、皆様
山形県【米沢牛の畜産農家を訪ねて】の感想を有り難うございます。
春馬さんが遠藤さんを訪ねた時期は雪景色だったのですね。
とっても寒かったと思いますが、前日に宿泊された小野川温泉で露天風呂からの雪景色はさぞかし美しかっただろうと想像しました。
「さいっっこーでした。」と仰った春馬さんの嬉しそうな笑顔が浮かびます。
私は子供の頃に、埼玉の田舎に住んでいた時期があって、学校帰りに牛小屋や豚小屋がありました。ある日の学校帰りに、偶然にも子牛の出産シーンを見学させて貰えて、本当に感動した。と言うか、産まれてすぐなのにヨチヨチと立ち上がる子牛の力強さが愛おしくてたまらなかったです。
生き物であり命を育てるお仕事を考えると、愛情を持って育て上げても必ず別れがやって来るという切なさもあるし、本当に大変なお仕事ですよね。
和彦さんが最後に仰っていた、「最近は田んぼを辞める人が増える中で、土地を活用して子牛を生産しないか?」と行政に提案されているとの事。町に雇用も生まれるし地域も活性しますものね。
そのお話を聞いた春馬さんの「未来が楽しみになりました。」という言葉が、とても印象的でした。
林檎さんが紹介して下さったサイトでも米沢牛について学びました。
LIVE JAPAN 山形の絶品ブランド牛【米沢牛】とは?基礎知識からおすすめ料理まで徹底解説というサイトでは、お店で食べるべき米沢牛と家で食べるべき米沢牛のオススメを紹介されています。
🍎林檎
希望様 皆様
山形県米沢牛の感想を有難う御座います。
LIVE JAPAN 山形の絶品ブランド牛【米沢牛】とは?基礎知識からおすすめ料理まで徹底解説のサイトを拝見しました。
希望さんご紹介のサイトは、大変分かり易く勉強になりました。
経産牛より未経産牛などが美味しいとの記載を読んでいると、なるほどとは思いながら、改めて、家畜と言われる動物たちの運命をふと考えてしまいました。
私達は、こうした動物たちのお陰で、美味しいものを頂くことが出来るのだと。
食物連鎖・殺生・ビーガン・ベジタリアンという言葉も浮かぶのでした。
希望さんが仰る、「生き物であり命を育てるお仕事を考えると、愛情を持って育て上げても必ず別れがやって来るという切なさもあるし本当に大変なお仕事ですよね。」
その通りだと思いました。
また、仔牛の出産シーンを見学されたお話に、生命の素晴らしさを幼いころに実感できたという貴重な体験は、希望さんの生涯にとって得難い経験だと思いました。
私は、ビーガンでもベジタリアンでもないので、今後、美味しいお肉を頂くときは、感謝の気持ちを忘れずに、生産者さん達の想いを想像しながら、味わいたいと思いました。
🕊💖希望
林檎様、strawberry様、皆様
幼い頃に経験した仔牛の出産シーンや、産まれたての子豚達の保育も見学させて貰った事があり、貴重な体験だったと思います。あの感動の体験で、命の有り難みを深く感じる事が出来ました。
いま『日本製』の後半戦に突入していますが、大人になってから忘れ掛けていた事を再び思い出させてくれる『日本製』を巡る旅は、今回も大切な何かを春馬さんが投げ掛けてくれているようで、そこに林檎さんやstrawberryさんが更に膨らみを持たせてくれています。
私もベジタリアンではないので、遠藤さんを始めとした日本全国にいる沢山の畜産農家さんのお陰で美味しいお肉を頂けています。また改めて感謝しながら味わいたいと思います。

🍓strawberry
林檎様、希望様、皆様
山形県[米沢牛の畜産農家を訪ねて]の感想をありがとうございます。
米沢牛の歴史や定義など、米沢牛について色々と知る機会になりました。米沢牛は、希少性の高い良質なお肉なのですね。
山形のおいしいお酒やワインと共に、春馬さんも絶賛した米沢牛を味わいたいです。
遠藤さんの米沢牛の飼料は、くず米を煮たものに、蒸した大豆と麦、とうもろこしなどを加えていて、代々改良を重ねた独自の飼料があるとのこと。
四大和牛の一つの松阪牛は、地元三重です。松阪牛は、育ち盛りの牛達の食欲増進の為にビールを与えたり、飼料にきな粉や糖蜜を混ぜたりします。美肌の為に焼酎でマッサージをしたりすることもあります。畜産農家で工夫もそれぞれです。
松阪牛は、甘く上品な香り、ヘルシーで良質な脂肪、すぐに溶けてまろやかです。
米沢牛や松阪牛などの畜産農家でそれぞれ飼料など工夫も様々で、手間をかけて良質なお肉になるように努力をされています。感謝の気持ちで、お肉を味わいたいと思います。
希望さんの仔牛の出産の場面を見学されたのは貴重な体験ですね。貴重なお話をありがとうございます。
林檎さんのお話の中に、上杉鷹山公がありましたが、米沢織を広めた方です。米沢織についての歴史や織物体験などの情報などがあるので紹介させて頂きます。関連URLをご覧ください。
山形は、春馬さんが宿泊された小野川温泉や銀山温泉などがあるので、いつか行きたいと思います。春馬さんが取材で訪れた小国町の役場のFacebookに雪景色の素敵な写真があるのでアップさせて頂きます。
この数日、天外者でお肉を食べる場面を観たり、日本製の米沢牛の話題に触れたりしているので美味しいお肉を食べたくなりました。
丁度カタログで頂いた松阪牛があるので、感謝しながら味わいたいと思います。

🍎林檎
strawberry様
松阪牛は三重県のものでしたね。三重県は、伊勢海老しかり、高級なものの宝庫ですね。
米沢織について教えて頂き有難うございます。米沢織は、光沢が美しいのですね。
“日本で初めて”人工絹糸(レーヨン)を発明したのが、大正時代に、米沢高等工業学校(山形大学工学部)の教授であった秦逸三(はたいつぞう)さんという方なのですね。
現在の帝人株式会社の先駆けとなる、帝国人絹株式会社を米沢市に創設したのですね。
また、二部式着物というのが珍しかったことと、染織工房わくわく舘のシルクスカーフが
素敵ですね。わくわく館内の紅花染色体験の中で販売されていますね。
そして、春馬さんが取材で訪れた小国町の役場のFacebookの雪景色の写真。
抜けるような真っ青な空と、純白な雪景色、清涼感があり心が洗われるようですね。
『自然の美しさに敵うものは無いのではないだろうか?』と思わせられますね。
★以前ご紹介の、山形県公式ホームページ内の米沢織のサイトは、現在観ることができないようでしたので【山形県】米沢織|とうほく知的財産いいねっとを掲載させていただきました。
NHK連続ドラマ「おしん」の舞台は、山形県の庄内だったのですね。随分と昔なので忘れていましたが、ドラマや映画のロケ地となるような家屋や風景が今も残っているのですね。
日本には、まだまだ知らない事が沢山あるのだと実感しました。

🕊💖希望
strawberry様
米沢織のご紹介を有り難うございます。米沢織の色合いの鮮やかな光沢の美しさに目を奪われました。光沢で一段と華やかさが増していますね。
strawberryさんの三重県には松阪牛がありますね。以前に伊勢神宮参拝の帰りに松阪牛を頂きましたが絶品でした。
小国町の雪景色は溜息の出る銀世界ですね。この景色を実際に見たら何もいらない!って、感じですね。春馬さんは露天風呂から美しい銀世界を見ることができたのですよね。
きっと、束の間のひととき癒やされた事でしょうね。strawberryさん素敵な情報を有り難うございました。
まゆ2307さん作

🐎👠Yokoharuma
林檎様、希望様、皆様
思い出しました。東北大震災の後、どのくらい経った頃だったでしょうか。
私は年配の友人と一緒に、仙台付近に住む宣教師さん達を訪ねました。その際、石巻市にまで足を伸ばしました。その時の光景は、体験していない私が軽々しく口にしてはいけないという思いが未だにありますので止めておきます。一泊して仙台に戻りました。
林檎さんのご子息は、仙台にいらしたのでしたか。どれほどの事だったのかお察しします。
ところで、三陸海岸はお勧めです。とっても綺麗な海です。ハワイの海に負けないと思いましたよ。私は、岩手県出身です。小学校の修学旅行は浄土ヶ浜でした。
カネダイさんは有名ですね。気仙沼はまだ行ったことないので、フカヒレ食べに行ってみたいです。
春馬さんは、撮影中だったのですね。彼は常に自分の仕事の価値を求めて、悩み迷いながら歩んでいたのですよね。
単にアイドルだ、イケメンだ、が話題に登る芸能界は、三浦春馬向きではなかった。
おっと、話しが外れました。
『日本製』の中で語っていますね。現実と向き合い、前を向く
是非、コロナ禍が終わったら東北旅行したいですね。北海道まで、いや日本全国へ、ですね。

Strawberryさん作
🍎林檎
Yokoharuma様
一足早く、次回の岩手県のお話を有難うございます。浄土ヶ浜の写真をネットで拝見しました。とっても美しい海岸線、そして海の色。
私の住む札幌は、近い海は石狩湾くらいで、少し足を延ばして小樽の海、つまり日本海側です。やはり、海は太平洋側が美しいイメージが強いです。
日本海側は、偏西風による厳しい風と荒れた海といったイメージですね。勿論、穏やかな時もありますが、演歌で歌われる中にも、荒れた海のイメージが
思い浮かびます。
『日本製』鳥取砂丘のラッキョウ作りも、厳しい日本海側の風を受けて育ったなどというフレーズがありましたね。
「2011年のその時の光景は、体験していない者が軽々しく口にしてはいけないという思いが未だにありますので止めておきます。」というYokoharumaさんの言葉にはうなずけます。
当時の東北の方々のお気持ちやご苦労を考えると、本当に言葉になりませんね。
浄土ヶ浜も、本来の美しさが戻って良かったです。
Yokoharumaさん、東北のお話を聞かせて頂き有難うございました。
🐎👠Yokoharuma
林檎様
早速の返信ありがとうございます。お忙しい毎日をお過ごしのことと思います。
もう、とっても恐縮です。『日本製』によって、日本全国を歩いている気分になります。
ありがとうございます。
